
今回はショアジギングタックルについてです。ロッドの解説を中心に、リールやライン、ルアーの選び方や種類、組み合わせについてもご紹介しています。青物の釣り方で必要な情報はコレでバッチリ!ショアジギングタックルを揃えて人気の青物を釣りましょう。
※2025年11月6日更新
ショアジギングタックルを揃えよう!
初心者向けタックルの揃え方を紹介

海の人気ルアーゲーム、ショアジギングのタックルをまとめてご紹介します。ロッドや、リールの選び方を中心に、各ロッドの特徴や組み合わせるリールの種類、基本的な仕掛けについて初心者にもわかりやすく解説しています。購入に向けて選び方を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
ショアジギングで狙える魚
人気ターゲットは大型青物

ショアジギングが人気の理由はショアから大型回遊魚が狙えるというところにあります。中でも人気の青物御三家と呼ばれるブリ・ヒラマサ・カンパチをはじめ、南方では人気のロウニンアジ(GT)やマグロといった、ドリームフィッシュを狙うこともできるロマン溢れる釣り方です。
ショアジギングロッドの長さの選び方
バランスが重要

ここからはショアジギングロッドの長さの選び方をご紹介します。基本的にショアジギングロッドは8フィート台の短いものから、10フィートを超える長いものまで様々です。釣り方でそれぞれに長所と短所があるので、自分の釣り方に合ったバランスの良い長さを選ぶことが重要です。
長いロッドのメリット・デメリット
飛距離は出るが、扱いにくい

まずは10フィートを超えるロッドの基本的な長所と短所をご紹介します。表を見ていただくと分かるとおり、10フィート以上のロッドはルアーをより遠投することができます。その反面、ロッドが長い分ルアーの遠投にコツが必要だったり、狭い磯での取り回しが悪かったりと、初心者には操作が難しい部分もあります。
| 操作性 | 飛距離 | メタルジグ | プラグ | |
| 8フィート〜9フィート | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 10フィート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10フィート以上 | △ | ◎ | △ | ◎ |
プラグが扱いやすい
飛距離や操作性の他に、10フィート以上のロッドはティップが繊細でプラグが扱い易い特性もあります。足場の高い堤防や磯では長いロッドが基本的に有利です。しかしメタルジグなどの重いルアーを遠投したり操作する際に、ティップの反発力が弱く疲れやすいので注意が必要です。
短いロッドのメリット・デメリット
初心者でも扱いやすい長さ

続いて8フィートから9フィート台のやや短いロッドの基本的な特徴を見てみましょう。先程解説した10フィート以上の長いロッドと正反対の特性になっています。8〜9フィートの短いロッドは操作性が良く初心者でも扱い易く人気ですが、ルアーの飛距離が出にくいというデメリットがあります。
| 操作性 | 飛距離 | メタルジグ | プラグ | |
| 8フィート〜9フィート | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 10フィート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10フィート以上 | △ | ◎ | △ | ◎ |
メタルジグが扱いやすい
短いショアジギングロッドは竿全体が強めに作られているものが多く、そして操作性も良いためメタルジグは非常にしゃくりやすいです。プラグも足場が低いポジションであれば問題なく操作可能ですが、足場の高い堤防や磯、強風下においてはプラグの操作が少し難しくなります。
ロッドの長さのまとめ
長いロッドは飛距離を出せるが、操作にコツがいる
短いロッドは扱いやすいが、飛距離が出にくい
初心者には9.6〜10フィートがおすすめ
ショアジギングロッドの硬さの選び方
メタルジグの重量で考えるロッドの硬さ

80g以上のメタルジグを使って大型青物を狙うショアジギングでは、重いルアーを遠投できると同時に、大型の青物とファイトができる強さも必要とされます。そこでまずは、扱うメタルジグの重さごとに、それぞれの硬さをご紹介します。 表のようにショアジギングロッドの硬さはMH以上が必要とされます。比較的水深の浅い堤防などではMHで十分ですが、地磯や沖磯などの急流で水深の深いポイントでは重量級のルアーが必要ですので、H以上のロッドの硬さが必要になります。
| MH | H | HH(XH)以上 |
| 40〜80g | 80〜120g | 120g以上 |
キャストウエイトの注意点
各ロッドのキャストウエイトの表記は必ずしも最適とは限りません。例えば40〜90gまでのキャストウエイト表記の場合は、間をとって50〜80gが最も扱いやすい重量となる場合が多いため、購入前にキャストウエイトの表記を良く確認する必要があります。
狙う魚のサイズで考えるロッドの硬さ
続いて釣りたい魚のサイズに合わせたロッドの硬さの選び方をご紹介します。クラス表記と実際のロッドの硬さはメーカーによって様々なのであくまで目安として考えて欲しいのですが、初心者にはMH〜Hまでのロッドで十分対応できます。HHロッドは特大クラスの魚を狙うことができる反面、操作も難しくなるので初心者にはあまりおすすめできません。
| MH | H | HH(XH)以上 |
| 5kgまで | 5〜10kg | 10kg以上 |
フィールドで考えるロッドの硬さ
最後に、堤防や磯などのフィールドによるロッドの硬さの選び方を紹介します。表は目安ではありますが、比較的水深が浅く、魚のサイズも中型までの堤防であれば扱い易く人気の高いMHがおすすめです。沖堤防〜沖磯では水深によるジグの重量、そしてそのエリアで釣れる魚を考慮して、H以上のロッドの硬さを選ぶ必要があります。
| MH | H | HH(XH)以上 |
| 堤防 | 沖堤防〜沖磯 | 離島 |
硬さ選びのまとめ
ここまで解説したように、ショアジギングロッドの選び方はなかなか複雑です。今回紹介した目安も全ての状況に当てはまるわけではないため、初心者の方は周辺エリアの釣り場や狙える魚のサイズなどに詳しい地元の釣具店でスタッフに相談してみるのが安心です。
ロッドの硬さのまとめ
使うメタルジグに合わせて硬さを選択
狙う魚に合わせて硬さを選択
%P_LINK%4969363301734
ショアジギングリールの選び方
最も重要なリール

ショアジギングではメタルジグをしゃくったり、大型回遊魚とやりとりをする際など常にリールに負荷がかかり続けます。また、不意にリールが海水を被るシーンも多くリールに耐久性が必要です。リールの選び方は大きさやギア比など、選び方や組み合わせも複雑ですので詳しく解説します。
基本は8000番
ショアジギングで最もスタンダードなリールの番手は8000番です。8000番はH以上のほとんどのロッドに合わせることができ、ベーシックなPE4号を300m巻ける点においてとても万能です。
| リール番手 | 使用ライン | ロッドクラス |
| 5000 | 1.8〜2.5号 | MH |
| 6000 | 2.5〜3号 | MH |
| 8000 | 3号〜4号 | H以上 |
| 10000以降 | 4号以上 | H以上 |
ショアジギングリール:ギア比の選び方
基本はハイギアでOK!

ショアジギングで使用するギア比は基本的に4種類です。パワーギア、ノーマルギア、ハイギア、エクストラハイギアの4種類に分類されます。中でも最も人気で基本となるギア比はハイギアですが、それぞれのギア比の特徴や使い分けを表で解説します。
| ギア比 | メリット | デメリット | メタルジグ | プラグ |
| パワーギア(PG) | 最も巻き上げパワーが強い。アクション時、ファイト時共に負担が軽くなる。 | ハンドル1回転あたりのライン回収量が最も少ない。 | ○ | △ |
| ノーマルギア | PGの次に巻き上げパワーが強く、軽く巻くことができる。 | HGと比較して、ハンドル1回転あたりのライン回収量が少ない。 | ○ | △ |
| ハイギア(HG) | 巻き上げパワーとライン回収量のバランスが良く、様々なシーンで使いやすい。 | PG、ノーマルギアと比較してハンドルの回転が重い。 | ○ | ○ |
| エクストラハイギア(XG) | ハンドル1回転あたりのライン回収量が最も多く、素早く糸ふけを回収することができる。 | 他のギア比と比較して、圧倒的にハンドルの巻きが重い。 | △ | ○ |
ハイギアとパワーギアの使い分け
パワーギア系は巻き上げパワーが強く、オフショアジギングで特に効果を発揮します。その反面、遠投してルアーを動かすショアジギングでは、糸ふけの回収時など素早さが求められるシーンも多く、基本的にはハイギア系を選ぶアングラーが多いです。
おすすめのギア比
表を見るとわかるように、ギア比にはそれぞれ長所と短所があります。ショアジギングをこれから始める初心者におすすめのギア比はズバリ「ハイギア(HG)」です。ハイギアは1回転あたりのライン回収量も多く、釣り方によらず万能に使えます。
リール選びのまとめ
番手は8000番を基準に選ぶ
初心者にはHG(ハイギア)がおすすめ
%P_LINK%4969363043658
ショアジギングタックル:メタルジグの選び方
メタルジグの選び方を紹介!

続いては基本的なメタルジグの種類を見てみます。重量やカラー、素材や形など様々なものがあるメタルジグの特徴をチェックしてみましょう。また今回はこれから初める方にも使いやすいものも紹介します。何を選ぶか迷った時には是非参考にしてみてください。
ショアジギングで使うメタルジグの重さ
ショアジギングで使用するメタルジグは80g以上がメインです。ショアジギングで狙う大型回遊魚は、潮の流れがよく、ある程度の水深があるエリアに潜んでいるため、重量級のメタルジグでなければボトムまで沈めることができません。 この表はあくまで目安です。エリアによって使う重量は大きく異なりますが、沖磯などのより大型の回遊魚が狙えるポイントでは重いメタルジグを使用することが多いです。
| 重量 | おすすめの釣り場 |
| 60〜80g | 沖堤防、地磯 |
| 100g以上 | 沖磯 |
重量選びのポイント
メタルジグの重量は重すぎても軽すぎてもいけません。軽すぎるとボトムが取れませんし、重すぎると早く着底してしまい魚にアピールできないからです。初めてのポイントで、流れや水深がはっきりしない時には、重量の選択肢をいくつか用意しておくと安心です。
メタルジグの素材
メタルジグの素材は主に鉛、鉄、タングステンが存在します。これらの素材はそれぞれ異なる特徴を持っており、使い分けることで青物の釣果を伸ばすことができるのです。 表のようにメタルジグの素材による違いを理解しておくだけで、釣れない状況を打破することも可能になってきますので、是非覚えておいてください。
| 素材 | 特徴 |
| 鉛 | 一般的なメタルジグ。大量生産に向いた素材で、比較的安価に買い求めることができる。 |
| 鉄 | 鉛と比較して比重が軽くゆっくり沈むため、早い動きに反応しない低活性の青物に対して有効。 |
| タングステン | 鉛と比較して比重が重く、同じ重さでも小さく作ることができる。ベイトは小さいが、重いジグが必要な際に有効。 |
メタルジグの形状
メタルジグのアクションに最も影響が出るのが、本体の形状です。様々な形状がありますが、今回は代表的な3つのタイプをアクションと合わせてご紹介します。 表のようにメタルジグの形状によってしゃくった時やフォール中のアクションが全く異なります。好活性時はスリムタイプで大きくアピールをして誘い、食いが悪い際にはスロータイプでゆっくり誘うなど、状況に合わせた使い分けが重要です。
| 形状 | 特徴 |
| スリムタイプ | 潮流の影響を受けにくく、素早くフォールさせることが可能。大きなスライドアクションでハイアピール。 |
| 標準タイプ | よく見る一般的なメタルジグの形状。ワンピッチジャークやジャカ巻きなど様々なアクションに対応。 |
| スロータイプ | オーバル形状でゆっくりと沈む。ひらひらとしたフォールアクションで誘うことが可能。 |
メタルジグのカラー
最後にメタルジグのカラーについてです。どの色が絶対に釣れるということはありませんが、青物系はグロー系に反応がよく、特にマズメ・日中問わず使うことのできる「ゼブラグロー」カラーは外せません。他にも定番のブルピンやシルバー系のカラーも揃えておくと便利です。
メタルジグの選び方のまとめ
ジグの重量は使うフィールドによって選択
素材にも注目 アクションによって形状を選択
ベーシックなカラーをベースに揃える
%P_LINK%4953873331428
%P_LINK%4969363138057
ショアジギングタックル:ラインの選び方
道糸はPEを使おう!

ショアジギングでは、飛距離と感度に優れるPEラインがおすすめです。特に大型の青物を狙うショアジギングでは、魚とのやり取りの最中に海中の岩にラインが擦れて切られることのないよう太めの仕掛けを使うことが多いです。 このように地磯や沖磯で使用するPEラインの号数はこれと決まっているわけではありません。堤防でのショアジギングでは飛距離を優先してやや細めのPEラインを使うことが多いですが、磯場では4号を基本に状況や狙う魚のサイズに合わせてPEラインの太さの調整を行います。
| PEラインの号数 | 釣り場 |
| 2号〜2.5号 | 堤防・沖堤防 |
| 3号〜8号 | 地磯・沖磯 |
リーダーは太めのフロロカーボンを!
ショアジギングでは道糸をPEライン、リーダーには太めのフロロカーボンを使用します。これは主に、ファイト中のラインブレイクを防ぐためです。
リーダーの長さは、堤防などであれば1~1.5m前後、磯などの擦られて切られるリスクが高い場所では3m以上取る場合もあります。
| ショックリーダーの強さ | 釣り場 |
| 30〜60lb | 堤防・沖堤防 |
| 60〜120lb | 地磯・沖磯 |
ラインの選び方のまとめ
PEラインは2号以上を選択
リーダーは60lb以上を選択
%P_LINK%4996774274869
%P_LINK%4582550710876
%P_LINK%4562398222588
%P_LINK%4562398222618
あると便利なグッズもチェック
ランディングネットは必須!

最後にショアジギングで欠かせない道具をご紹介します。ランディングネットは玉網ともいいます。足場の高い堤防や岩場から重量のある魚を引き上げる際に便利です。ランディング時のロッド破損も良くあるので、初めての方は極力ランディングツールを使って魚を引き上げます。
%P_LINK%4996774059961
%P_LINK%4996774111577
プライヤー


これはスプリットリングを開けたり、魚の口からフックを外す際に使用するペンチのような道具です。ショアジギングではアシストフックの針先が鈍ることが良くあるため、こまめなフックチェンジが必要。フックチェンジを素早く行うためにも、プライヤーは必須アイテムです。
%P_LINK%4996774274913
%P_LINK%4996774331968
フィッシュグリップ

青物を釣りあげたあと、魚の口からルアーのフックを外す際に役立ちます。素手で魚を抑えてフックを外そうとすると、魚が暴れてフックが手に刺さってしまうことも良くあります。安全に魚をホールドしておくためにフィッシュグリップも必須のアイテムです。
%P_LINK%4996774332569
グローブ

100g前後の重量のあるメタルジグをキャストする際には、キャスティンググローブやフィンガーグローブが便利です。キャスト時に人差し指を怪我してしまう恐れがあるため、その予防として効果的です。また、磯でのショアジギングの場合は不意の転倒時などに手を守るため、フルフィンガーのグローブを着用しましょう。
%P_LINK%4996774149709
ショアジギングタックルで釣りに出かけよう!

ショアジギングは初心者でも様々な種類の魚を狙うことができる人気のルアーゲームです。初めてでも釣り方と必要な仕掛けの組み合わせをしっかり理解しておけば誰でも簡単に初めることができるので、初心者の方もぜひチャレンジしてみてください。





































































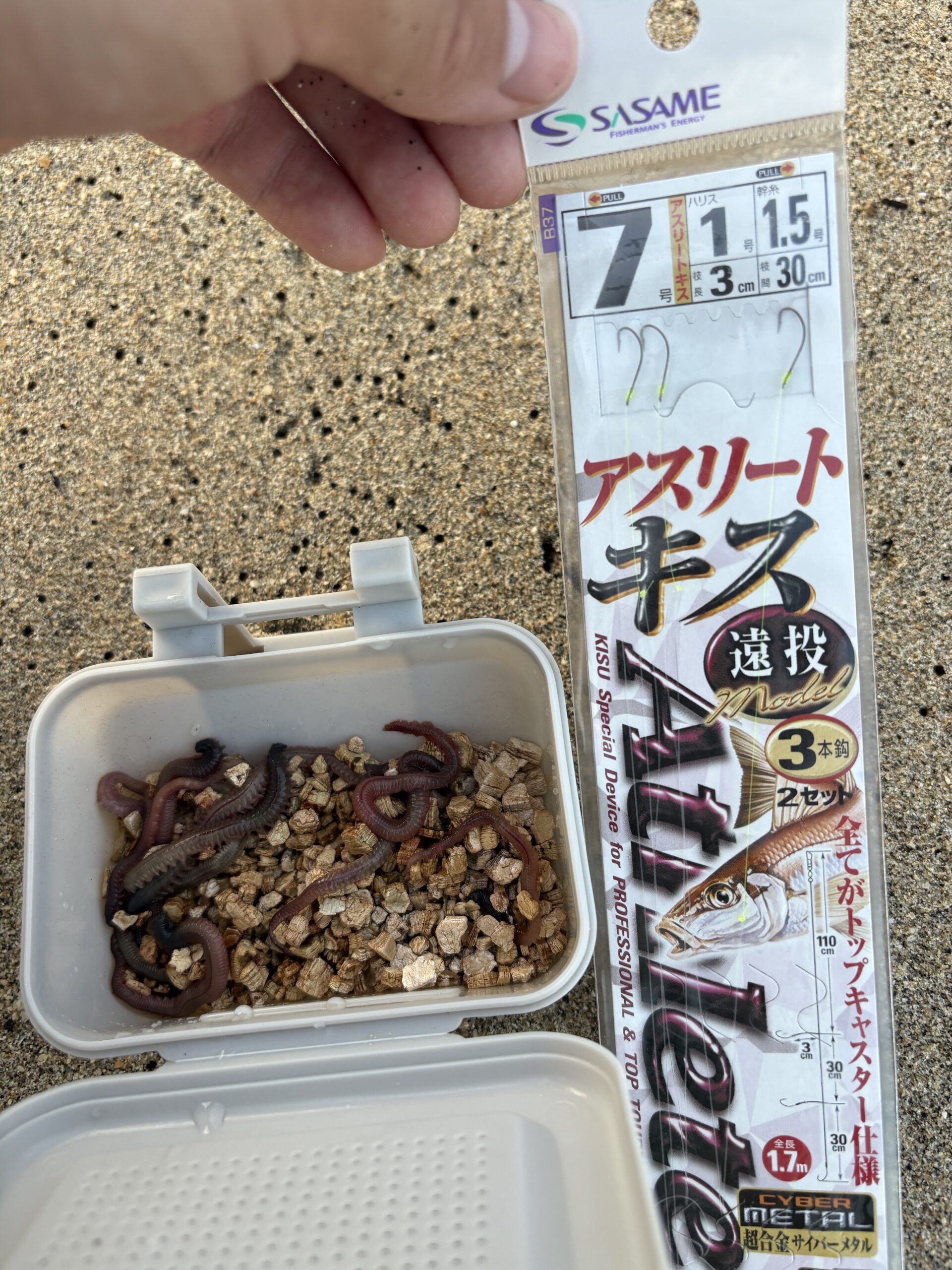



におすすめの釣り特集!地域毎にも釣れる対象魚をご紹介!-1-2000x1200.jpg)









































